The Henry Taube Institute
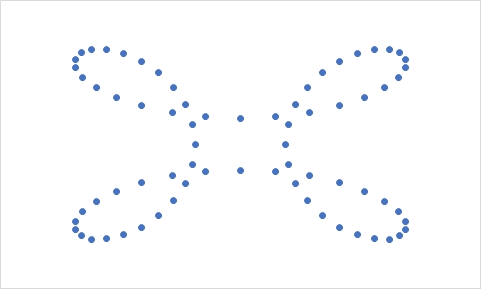
研究員

研究所長
長谷川 泰
(Tai Hasegawa, Ph.D.)
東京大学理学部化学科卒業、同大学大学院理学系研究科修士課程、同大学大学院博士課程修了(理学博士)。ポーランドアカデミー物理化学研究所で客員研究員を経験後米国スタンフォード大学化学教室に博士研究員として招聘される。研究主催者は当時ノーベル化学賞を受賞されたHenry Taube教授。その後同教室で正研究員、分子医科学研究所の主任研究員、テニア後研究教授。米国永住権を得た後OHT研究教育機構の機構長を兼任。Linus Pauling教授の逝去後に(教授の研究所の残存施設を継承した)Henry Taube研究所の所長に就任して現在に至る。尚この間スタンフォード大学化学教室と東京大学理学系大学院の客員を適宜兼任する。専門は錯体化学を経て自然哲学から哲学科学。歴史的思想家を目指す。

シニア・リサーチ・フェロー
工藤 明
(Akira Kudo, Ph.D.)
1977年3月:東京工業大学総合理工学研究科修士課程終了 薬学博士
九州大学生体防御医学研究所助手・助教授、バーゼル免疫学研究所研究員
1994年12月ー2017年3月:東京工業大学生命理工学研究科教授
2017年4 月:東京工業大学名誉教授
免疫研究ではプレB細胞レセプターを発見し、B細胞分化に必須のレセプターであることを証明した。この研究の主論文はアメリカ免疫学会誌の免疫研究の基盤を作った論文に選ばれている。
また骨研究では主に以下の4つの業績にまとめられる。
(1) 破骨細胞分化系を確立し、TNF-aが破骨分化因子であることを明らかにした。
(2) OB-カドヘリン/カドヘリン-11を発見し、OB-カドヘリンは頭蓋骨形成に寄与することは明らかにした。
(3) 歯根膜・骨外膜に発現しているマトリックス蛋白質を、ぺリオスチンと命名した。ぺリオスチンは歯と骨のリモデリングに機能し、特にコラーゲン架橋を促進する。
(4) メダカの骨形成のシステムを確立し、多くの変異体から原因遺伝子を明らかにするとともに、造骨と破骨細胞を可視化したトランスジェニックラインを宇宙ステーションで飼育し、無重下での骨量減少を見出している。

プリンシパル・インベスティゲーター
植松 寧史
(Yasushi Uematsu, M.D., Ph.D.)
1983年:東北大学医学部卒業 医学博士
1985年:千葉大学大学院2年在学の後スイスバーゼル免疫研究所メンバー
1989年:Hoffman-La Roche中央研究所免疫部Senior Scientist
1991年:バーゼル大学教育研究センター免疫研究部研究員
1997年:Chiron Vaccines Reserach Center ウイルス免疫部門研究マネージャー
2008年:Novartis Vaccines Reserach Centerウイルス部長 を経て微生物分子生物部門Senior Research Investigator
2015年:Glaxo Smith Klein Reserach Center微生物分子生物部門Senior Research Investigator
2023年:ヘンリータウベ研究所に分子構造相互作用研究室を設立。
主な研究分野:
免疫学、主に獲得免疫の発生と分化、主要組織適合抗原の遺伝と多様性 ウイルス学、ワクチンプラットフォーム、殊にウイルスベクターとmRNA

プリンシパル・インベスティゲーター
中野 誠彦
(Nobuhiko Nakano, Ph.D.)
慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業、同大学大学院理工学研究科修士課程、同大学大学院博士課程修了、博士(工学)取得。学術振興会特別研究員を経て慶應義塾大学理工学部電子工学科助手として任用。スタンフォード大学集積システム研究センター(CIS)にて客員研究員を経験後、専任講師、准教授を経て現在電気情報工学科教授。研究対象は半導体プロセスに利用された非平衡プラズマをボルツマン方程式で数値的に解析するところから半導体工学のデバイス、回路に発展し、現在は集積回路設計とマルチフィジックスシミュレーションを行う。特に生体と繋がる集積回路に興味を持つ。
歴代の関連所長・研究員
特に我々に大きな影響を与えてくださった先生方

Linus Pauling
創建時よりの精神的支柱。厳密には当研究所の所長ではないが、敬意を持ってここに出させていただきます。

Henry Taube
名誉所長として指導いただきました。
学問的には無論、ご生涯は古代中国の賢人老子にも喩えられると弟子たちの尊敬を集めました。

Emile Zukerkandl
Linus Pauling研究所の所長、分子医科学研究所の所長を歴任。Pauling先生と共に分子時計の概念の提唱者でした。
特別研究室
分子構造相互作用研究室
Investigation Lab. for Molecular Structures and Interactions
主席研究員 植松寧史
生命現象には様々な側面があります。例えば自己の複製、エネルギーの取り入れとその活用など。この研究室では生体分子の構造と相互作用に焦点を当てていきます。
現在取り組んでいるのは抗原エピトープに強く結合できる免疫グロブリンの構造をコンピュータのみを用いてスクリーニングすることです。
従来までのモノクローナル抗体はヒトや動物由来の材料で与えられた抗原に特異的なものを探してくるやり方でつくっています。これを完全にコンピュータの計算のみで行うのが最終目標です。倫理的に人体に免疫することはできませんが、コンピュータによる仮想的な免疫によって例えばヒトの持つレセプターに対する治療目的の抗体も直接ヒト型で作成することが可能になります。これは抗体工学の大きなブレークスルーとなるはずです。
このアプローチは極めて野心的で現時点では確実な方法論すらありません。しかし時機を逸すること無く日進月歩のテクノロジーを使っていけば必ずや実現の道筋が見えてくると確信しています。
スタッフ

Chiba Nest Manager
田川 慧

Website Manager
鈴木 由莉子��

Palo Alto Nest Manager
金沢 知広